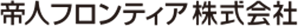帝人フロンティアの人々
ゼロから「イチ」を生み出す基盤開発
技術・生産本部
本部長付 基盤チーム
川上 将輝
技術・生産本部の本部長付 基盤チームにて長繊維の開発を担当。2021年に入社後、短繊維の開発に従事し、2024年に現在の部署へ異動。既存の考えにとらわれず、新しい糸を生み出す「0→1」の長繊維開発に取り組んでいる。
WHAT‘S YOUR FRONTIER?
私に求められているのは、帝人フロンティアからしか生み出せない素材を世に送り出すことです。所属している技術・生産本部では、会社からもそのミッションを託されています。最終的に自分の開発した素材が製品となって店頭に並び、それを見て「あの製品に使われている糸は自分がつくったのだ」と胸を張れる日を目指しています。

ゼロから「イチ」を生み出す基盤開発
入社後は、原糸や原綿の生産・開発を行う松山事業所の繊維技術開発に配属になり、短繊維の開発に携わっていました。その後、2025年に現在の技術・生産本部の本部長付 基盤チームに異動し、現在は長繊維の開発を行っています。同部署には私を含めて3人の研究員が在籍していて、それぞれが常に複数の開発テーマを同時並行で担当しています。
基盤開発の役割は、「ゼロからイチを生み出す」ことで、新しい繊維シーズを提案・開発する事です。まだお客様や消費者のニーズが顕在化していない段階で、社内からの「こういう糸がほしい」「こんな素材が必要だ」といった声を出発点に開発を進めていきます。トライアンドエラーを繰り返しながら、生産ラインに載せられるように技術のメカニズムを明らかにして、製造プロセスを確定し、形にしていくわけです。
繊維開発を植物に例えるなら、基盤開発はまさに「種そのものを作る」部署。種と育て方のレシピを用意し、次の部署へと託す位置づけです。ここで生まれた素材は繊維技術開発などに引き継がれ、次のステージへ進んでいきます。
アイデアが形になって技術がある程度確立され、最終的に生産ラインに乗るまでには、最低でも5年ほどはかかります。私は入社して5年目なのですが、先日、繊維技術開発課で取り組んできた開発品がやっと生産ラインに乗りました。数多くの研究開発を日々進行していますが、生産ラインまでたどり着けるのは、ほんの一握りです。
開発には多額のコストがかかりますから、生産ラインに乗る素材を開発するまでは、どうしても「会社にも社会にも貢献できていないのでは」と感じることもありました。だからこそ、開発を手がけてきた素材が生産ラインに乗って世に出ると聞いた時には、喜び以上に「ようやく社会に還元できた」「会社にとって利益を出せる人間になった」と、ほっとした気持ちが大きかったですね。

研究者として大事にしていること
前の部署でもポリエステル素材を使っていましたが、短繊維と長繊維とでは製法も考え方も全く異なります。異動してからは、本当に一から学び直す日々が続きました。最初は「何が分からないかすら分からない」という状態でしたが、上司が丁寧にフォローしてくださいました。「何が分からないのかが分かるまで付き合うから、今思っていることを、全部言葉にしてみよう」というところから始まって、本当に多大な時間を割いてくださいましたね。
今でも印象に残っているのが、「研究者は分析する手段を磨くことが大事だ」という言葉です。
特に基盤開発は、トライアンドエラーをただ繰り返すのではなくて、技術において根拠を分析し、法則を見いだしていくことが求められます。このことは、今でも日々意識しながら仕事に向き合っています。
また、基盤開発ではスケジュール管理やプロジェクトの選択など、裁量が大きい部分があります。それはやりがいの一つでもあるのですが、もちろん責任も大きいと感じています。社内で生まれるアイデアを形にするにあたっては、テーマの選定や取捨選択が重要です。中には、どこかの時点で割り切って新たな研究に進まなければならないタイミングも出てきます。次々と社内で新しいアイデアがどんどん出てくる中で、どのアイデアを深めていくかを見極めながら、できるだけ早く次の部署に託すことを意識しています。
今後はさらに広く、開発に関わっていきたい

基盤開発でアイデアを形にし、技術開発の部署にそれを託し、そこでさらに素材が加工されると、今度はそこに営業の方が加わり、お客様や生産工場の方々と一緒になって生地を作っていく。一つの糸が誕生して市場に出るまでには、こうした経緯をたどります。
その一連の流れの中で、私はまず素材開発の上流工程を経験したいと考えており、入社時からそうした思いを上司にも伝えていたので現在のキャリアを歩めていると思います。
今後はさらに下流の開発や加工にも携わり、経験を重ねていけたらと思っています。
エントリーはこちら